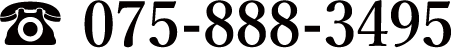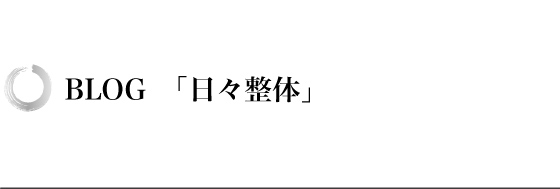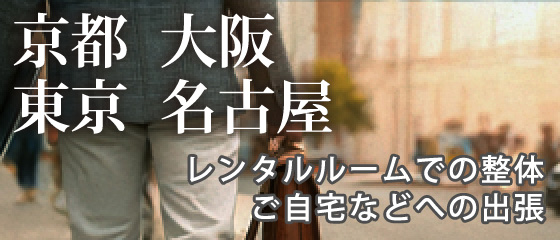不安症とパニック症:医学とは異なる整体の見方
パニック症、不安症というと、不安や動悸を起こしたりするものというのが一般的な解釈です。しかし、症状の実際は人によってかなり差があります。電車やバスに乗れないというようなケースにはじまり、自動車は乗れるけど高速道路に乗れない、電車に乗れるけど各駅停車でないと駄目、学校の教室に入れないなど、様々なケースがあります。ストレスや過去の経験から不安や恐怖が思い出されてその影響で起こると言われることが多いようです。
しかし、整体師である私は不安症、パニック症はそういうものとは、まったく違うものだと考えています。その最大の理由の1つは、私自身が実際にその症状を体験したことがあるからです。家族が入院してしまいこの先どうなるかわからないという状況で、仕事を休むこともできず、家、職場、病院をを延々と周り続ける生活をしていたときのことでした。
ある夜、突然の動悸とともに不安な気持ちになり寝つくことが全くできなくなりました。
実は、私自身は、そのような状態であっても案外冷静さを保っていて、
「これが噂に聞くパニック症という奴か。」
と喜んでいた記憶があります。
なお、翌日すぐに整体の師匠に体を見てもらい、すぐにこの不安症は解消することができました。すぐに整体したので深刻にならずに済んだのでしょう。
このような経験をしているので、
「これはストレスや過去の記憶は全く関係がない。」
と、はっきりと理解できました。
当時は不安に押しつぶされそうになりながら、極限の疲労状態でした。ですから、ストレスとは無縁とは言い難い状態です。しかし、整体の知識と技術を身につけている私には、自身の体に何が起こっているかをきちんと理解することができました。
パニック症のメカニズムを簡単に説明すると、
「心臓を上手に動かせなくなっている状態。」
ということがいえます。
背骨の状態を読み取ることができると、このことを理解するのはそれほど難しくありません。パニック症の根本的な原因は、胸椎1番、4番、腰椎1番、3番にあり、骨を観察をすると硬く弾力をなくしています。これらの背骨は脾臓と心臓の動きに関わる神経が通っていて、2つの内蔵の働きに深く関わっています。そのため、背骨に問題が生じると脾臓と心臓がスムーズに働かなくなるのです。
ただ、1つ注意することがあります。
それは脾臓や心臓そのものに問題があるわけではないということです。自動車に例えるとわかりやすいでしょう。アクセルを踏み込んでもエンジンの回転数があがらない状態なのです。つまり、エンジンそのものには問題がないにも関わらず、エンジンに送られるガソリンや空気が不足したり、回転数をあげるための信号がうまく伝わらないということです。このことが、医療において不安症、パニック症の原因をつきとめることを難しくしているのではないかと考えています。
多くの人にとって理解が難しいのは、背骨に異常が生じるということがどういうことかわからないという点ではないでしょうか。
最先端のレントゲンやMRIでは背骨の異常は判断ができません。また、近年の医療は、触診をあまり重視していないために、背骨に触れてその状態を判断する技術がありません。医療においては、検査数値のような客観的なものを重視する一方で、手の感覚という主観的な判断材料には頼らない発展を遂げてきている弊害なのだろうと考えています。
その点、整体師は手の感覚が主な判断材料です。
手の感覚に特化しているといってしまってもよいでしょう。ですから、容易に異常のある背骨を見分けることができます。
パニック症に対して、整体が医療と大きく違う点は、整体では根本的な異常を発見できるという点です。感情は体があってこそはじめて生じるものです。ですから、体になんらかの問題があれば、その人の感情に異常が生じることは不思議なことではないのです。
不安や心配の気持ちが高まるのは、脾臓や心臓が不安や興奮という感情と強く結びついているからです。簡単に説明するのであれば、脾臓に力が集まりすぎるとみぞおちに力が集まり不安が強くなり、心臓に力が集まりすぎると興奮して落ち着かなくなります。これは、脾臓や心臓の働きを制御する神経が緊張していると言い換えるとわかりやすいでしょう。
整体的な説明を加えると、内臓は必要に応じてその能力を高めたり静めたりします。しかし、それがうまくいかないときにその臓器に気が集まりすぎる、つまり力みが生じてしまうということです。そして、その内臓の働きに不調が生じると感情が影響を受けてしまうことになります。
もちろん、ストレスや過去の記憶によって内臓の働きが影響を与えることはあります。
しかし、大半の人は体の不調が感情に影響しているのです。実は、私自身はストレスや過去の記憶が原因でパニック症を起こしている人を見たことがありません。ですから、まずは体の不調を整えた上で、それでもパニック症の症状が落ち着かないかを確認するほうが確実で間違いのない対処法だと考えています。
もしお困っておられるという方はご相談いただければ、医療とは違った視点、技術、知識からアドバイスができるはずです。連絡先はホームページで確認ください。
体は神秘の宝箱、自律神経整体院でした。
医療が見逃すもの、整体が見つけるもの
年相応という言葉の意味
YouTubeで動画を公開しました。