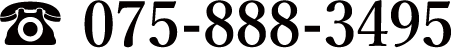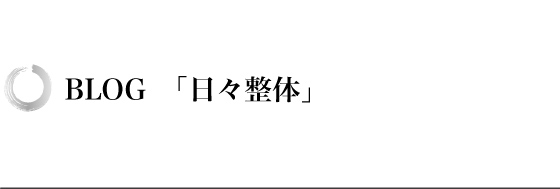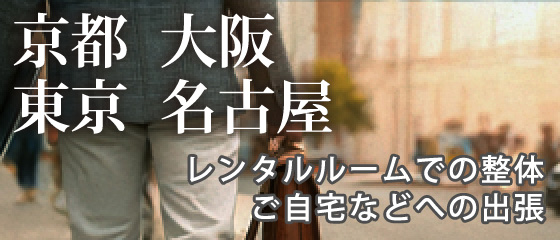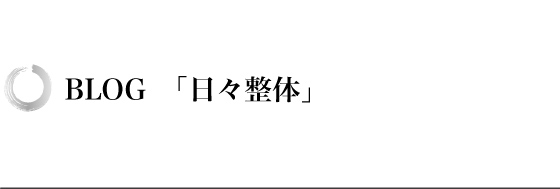
2013年09月27日
いくつかの療法や治療をかけもちでうけられる方がいます。
でも、こういう方でうまくいった人など一人もいません。少なくとも私は一人もそんな人をみたことがありません。
「体によいことをいくつもやっているのでその相乗効果で体が整ってくるのではないか?」
そう考えてしまうようですが、実際はまったくの反対です。
体を大きく変化させようと思ったときに考えべきは1点集中です。それがもっとも効率的です。
あれもやって、これもやってではぼけてしまって自律神経の状態が整ってきません。
ところが、1点集中、たとえば、
・骨盤を締める
・骨盤をあげる
・骨盤を開く
・交感神経を高める
・副交感神経を高める
ということにのみ集中して整体すると、自律神経の状態は大きく変化してきます。
二兎を追う物は一兎をもえず
という言葉ありますが、体にはこの言葉がもっともあてはまります。
ところが、この1点集中ができたときには、
一石二鳥
どころか、三鳥、四鳥以上の成果があがります。
体とはそういうものだと私は思います。
2013年09月12日
天高く馬肥ゆる秋
という言葉があります。
挨拶で使う言葉だそうですが、馬もまるまると太る良い季節だというような意味合いです。中国なんかだと北方民族が太った馬に乗って略奪しに来る季節という意味合いもあったそうです。
秋は実りの季節です。
いまの日本で生活すると季節を大きく意識することはないのではないでしょうか。野菜なんかは年中同じものが売っていたりしますから旬がいつか?なんてのはあまり意識しません。まぁ、旬をはずすと味がおちたり値段があがったりしますから敏感な人には何をいっているだという事かもしれませんが。
話を戻します。
秋というのは収穫の季節です。お米がとれる季節ですし、ぶどう、柿、栗、りんご、みかんなどの果物、魚類ではサンマ、イワシ、サケ、サバなど秋においしい食べ物がたくさんあります。
食欲の秋というとこういった美味しいものがたくさんあるから!
と、考えている人が多いようですが、実際は違います。人間の体も秋になると食欲がとまらなくなります。どうしてかというと、体が冷えるからです。
体が冷えると食欲が止まらなくなります。
体を冷やしたときに一番影響がでるのが、泌尿器なのです。泌尿器の働きがわるくなると胃酸が増えてきます。食いしん坊の体を胃酸過多なんていう言い方をするのはご存じでしょうか?胃酸が多い状態だと、いくら食べても満腹を感じることができません。いらくでも食べれるようになりますし、いらくでも食べたくなってしまうのです。
本来はこれでまったく問題なかったのだろうと思います。
なぜなら冬になると食べ物が極端にすくなくなるからです。秋にたくさんの栄養を蓄える。人はそうやって厳しい冬を乗り切ってきたのでしょう。そして、そうするために、体が冷えてきたときに、
たくさん食べることができる
そんな、体の状態を自然に作るようになってきたのでしょう。
もちろんこれは人間だけじゃなく、馬をはじめとする他の生き物でも同じような体の働きがあるのでしょう。それが、天高く馬肥ゆる秋という言葉につながったというわけです。
さて、これが今の日本という環境では非常に困った事を起こします。
食べ過ぎになるのです。
つまり栄養過剰になってしまうのです。今の日本人で冬になったからといってひもじい思いをするような人はほとんどいないことでしょう。
花や木に肥料をあげすぎたときに枯れてしまうように、人間も栄養過剰になると栄養中毒を起こして体がこわれてきてしまいます。
一昔前なら食欲の秋は必要な事だったのでしょう。
しかし、今のこの環境で食欲の秋は体を壊してしまうと言うことは知っておく必要があると私は思います。

2013年08月13日
体の悪い人は、気持ちが落ち込み気味です。
そして、そういう人は周囲から、
「もっと前向きになりなさい。」
と、いわれがちです。
そのせいで自分を責めはじめます。
「私が気持ちを前向きにしないから体が悪いのでしょうか?」
とよく聞かれるのです。
元気な人にはばかばかしいと感じるような話題ですが、体の悪い人にはかなり深刻です。そして、大きな勘違いをしています。
体と心、どっちが主体か?
というと、実は体が主体です。
だから体が整っていれば気持ちは自然と前向きになります。逆に体に問題があれば気持ちは後ろ向きになります。とても当たり前の事です。
気になった瞬間にみなさん人間がかわってしまいます。
体が整った人は、偉そうになったり、威張りだしたり、体が弱っていたときとは別人になっていくのをずっとみてきています。
体の状態で人間はそれぐらいかわってしまうのです。
だから、
「気持ちが後ろ向きで・・・」
という人は、まず体の状態をかえることです。
2013年07月16日
花がしおれてきたとにどうするか?
霧吹きをもってきて、花に一生懸命に水をかける人というのはまずいないことでしょう。
では、どうするかというと根から水を吸い上げることができるように根を整えてあげます。植物の場合だと茎をきって水にさすなんていう手もつかえますね。いずれにせよ、花には手をつける必要がありません。
実は人間の体も同じことがいえます。
今、一番多いのは耳鳴りの相談ですが、耳鳴りは耳の異常ではありますが、耳そのには問題がない事がほとんどです。だから、耳を一生懸命に手入れしてもほとんど意味はありません。これは耳鳴りで困っている人にいうとたいていすぐに理解できるようです。
さて、植物においては水を吸い上げれるようにしてあげると、花がきれいにさきます。
人間の体において、水を吸い上げれるようにするというのは、どういうことか?というと自律神経を整えるということになります。
人間の体のしくみを考えるととても簡単な理屈です。
2013年05月11日
平安時代には、医心方という本があったそうです。
日本最古の医学書といわれているもので、この中にはこういうことがかかれているそうです。
養生というものは、知識として理解するだけでなく、何度も繰り返して習得し、生まれながらにみにつけているようにしなければならない。身そなわれば自然に身体に良い結果があらわれる。習慣にしなければ効果はない。天性がおのずから自他に対して善であれば、あらゆる病気にかからず、禍乱災害も起こりようがない。これが養生の根底をなすものである。
思うに"養生"というのは、病気にかからないようちに病気の源を治める-つまり、病気を未然に防ぐことなのである。だから養生を志す者は、単に薬を服用したり仙人の食べ物や呼吸法を真似るというのではなく、さまざまな修行を同時におこなわなければんらない・・・
日本の古代医術 光源氏が医者にかかるとき 槇佐知子著 文春新書 より
平安時代の宮中医官であある 鍼博士丹羽康頼という人が編集したものだそうです。全30巻もあったのだとか。
わたしが普段いわんとしていることは、もうすでに1300年前に言われているというわけです。
終わりの方にある、
単に薬を服用したり仙人の食べ物や呼吸法を真似るというのではなく
という部分にちょっと笑ってしまいますね。
人間は、いつまでたっても考えることはたいしてかわらないということなのでしょうね。