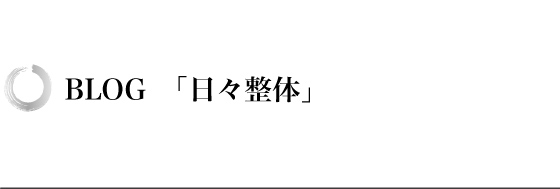父親が死亡して遺産の整理をしていて思った事は、
「もしかして自分には税理士としての才能があるのかもしれない?」
という事だったりします。
金銭の勘定は多くの人が面倒くさいと感じるようなのですが私にはそれが興味深いと感じるのです。どういう具合に税金が掛かっているのかを確認していくと、
「うまく考えてとりはぐれがないように。」
としっかり考えてあるなと感じてしまいます。
この感覚はサラリーマンにはわからないかもしれません。
私のような自営業者とサラリーマンの大きな違いは税金の収め方です。サラリーマンは税金をひかれたあとに口座にお金が振り込まれるのに対して、自営業者は一回手元にお金が入ってきてから税金を支払う訳です。
この違いは、おこづかいに税金がかかると考えるとわかりやすいかもしれません。
「あなたは毎月3万円のおこづかいがあるとします。しかし、そのうちの10%は年度末に税金として収めなくてはいけません。」
あなたのおこずかいの制度がこのようなシステムだったら年度末に税金分のお金をちゃんと残しておける人が果たしてどれぐらいいるでしょうか?おそらく全体の10%程度になるのじゃないでしょうか。ついでにいうと、このしくみのえげつなさが理解できたら、消費税がいかに厳しい税なのかということも合わせて理解できるかもしれません。確実に年度末に3万6千円ちゃんと用意ができているように段取りをしていても人生には何が起こるかわかりません。友人が立て続けに2人結婚してその祝儀、さらに身内が一人亡くなって香典が、と出費がつづくだけで脱税しないまでも追徴課税を請求される可能性があるのです。たったそれだけの出費で破綻することだってあるかもしれません。
話がそれたので戻します。
それで、こういう税に絡んだ事を調べていくと、
「案外、整体師より税理士に向いているかもしれない。」
と感じてしまう事がたまにあるのです。
税理士の資格をとるための試験なんていうと、無味乾燥な勉強をつづけなくてはいけないと考えていましたが、案外、面白がって勉強したかもしれないなんて思ってしまいます。好きな事を仕事にすると、あらゆることがうまくいくなんていう人生論を聞くことがありますので、もしかしたらそれで幸福な人生をおくれた可能性もありますね。
それに対して整体師はどうかというと、興味がない訳ではありませんがちょっと違う方向を向いているような気がします。私は何かに興味をもったときのその興味にたいしての打ち込み方というのは尋常ではありません。ずーっとそのことばかり考えて、本、雑誌、インターネットなどなどあらゆる情報チャンネルからその事の情報を取得しようとします。
ただ、人間の体についてはそういう事はありませんでした。
いっときは毎日本を数冊読んでいたような時期もありましたが、淡々、粛々と勉強をして情報を集めてという態度で健康という事に接するようになってきました。
「もっと熱心に取り組めばもっと上を目指せたのではないか?」
と、思うこともあったのですが、どうも違うような気がしています。
なぜかというと、現状の社会で熱心に健康と人間の体について勉強をしてしまうと、多分、おかしな事になってしまうと思うのです。それゆえに深い興味をもてなかったのではないかと。
例えば、人生が100年になるとかいうのがそうでしょう。他だと、人間は2050年までに人間は不死になれるというような思想です。
これはもう結論だけを述べてしまいますが、前者については、
「100歳まで生きるとして最後の10年寝たきりで100年生きたと喜べるのですか?」
という質問の答えを考えるとわかりやすいでしょう。
寿命が延びたとしてそれに応じて健康寿命が伸びるとは、私には決して思えません。もし、ピンとこないようであれば、お医者さんにいって、健康について相談したらすぐにわかるのじゃないでしょうか?たいていの問題は、
「歳のせい。」
で片付けられるはずです。
後者は、もっと簡単で不死になったらそれはもうホモサピエンス、つまり人間ではありません。ジョジョの奇妙な冒険の悪役で不死になったディオ・ブランドーの有名なセリフに、
「俺は人間を辞めるぞー!」
というものがあります。
ジョジョを見た事がない人でも、セリフぐらいは聞いた事があるかもしれません。私は人間を辞めてまで生に執着しないほうが幸せだと思います。
簡単に説明しておくと、多細胞生物である哺乳類はオスとメスという性を獲得すると、寿命を制限する必要が生じました。なぜかというと、近親で子供ができてしまうと遺伝子に異常が生じて奇形の子供の生まれる可能性が高まってしまうからです。例えば、中世のハクスブルグ家は、近親婚を繰り返すことでヨーロッパの支配を確立した訳ですけど、その結果、生まれてくる子供が健全であることはほとんどなかったそうです。
我々、哺乳類は性をもつことで環境の変化に対応する能力を飛躍的に高めたのです。
その代償として寿命も持つことになりました。なお、私は厳密にいうと代償ではないと思うのですけど長くなるのでここでの説明は省きます。人間という生物が繁栄するために、我々は適度な期間生きて、次の世代が誕生したら死ぬ必要があります。近親交配が起こらないようにする必要があるのです。この事は生物学をかじってみると割と初歩のところででてくる話なんですが、医学はこういう事を無視して進歩しようとするから困った事になるだろうと思いますね。
ちなみに、ちょっと長生きしたぐらいでそんなにかわらないだろうと思うかもしれませんが、野性の生き物では強いオスが3世代ぐらい生きていると周囲のメスがすべて近親になるとかいうモデルケースを見たことがあります。人間の場合、寿命がなくなったときにどのように価値観が変化するかわかりませんから、どういう事になるか想像がつきません。だから、不死という概念はもうちょっと慎重にすすめないといけないのです。
現在はこのことに加えて遺伝子で能力が決まるという考え方になってきていますから、寿命がなくなった時には優秀な男性と女性の子供しか望まれないなんて事になっても全く不思議はありません。知能や運動能力の高い人間の子供以外は必要とされない社会など、やはりどのような事になるのか想像もつきません。
また、こんな事になってしまうのは、人権を大切にしようという考えが根元にあるからです。
死は、人権侵害なので死んではいけないとかいう事が国連の憲章だかに書いてあるそうです。もっと、シンプルにいうなら個人を大切にするという発想が根本にあると、人権を守るためには人間は死んではいけないという結論になるのです。しかし、種の繁栄のために死ななくてはいけないというのは、性をもつ哺乳類であるため必要な事です。ところが、種の繁栄と個人のどちらを大切にするのかというと、現在は後者の個人がもっとも大切で価値があると考えられているのです。
ピンとこない場合は、映画やYouTubeなどの映像を例にするとわかりやすいでしょう。
「100日後に死ぬワニ」というマンガが映画化された時に、「100日間生きたワニ」とタイトルを変えられたのは多くの人がご存じでしょう。そして、YouTubeでは、死という単語を使った動画は削除されてしまいます。人権を重視した結果、死を許さないという考え方が拡がっているという事です。
それで、
「こんな事を考えている私は、整体師に向いていないのではないだろうか?」
なんて思ってしまう訳です。
限りある期間、幸福に生きるために健康になるという考えはほとんどの人には受け入れられないでしょう。整体師だからこそ、このように考える訳ですが・・・。
ところが、医学と健康について真剣に興味をもってしまうと、
「人は死んではいけない、人権がもっとも崇高で大切なものだ。」
と、考えるようになってしまうだろうなぁと、こうなると医者になるしか選択肢がなくなってしまうような気がします。でも、そんなのは絶対に嫌な訳です。
仕事を繁盛させようと思えばやることは簡単です。
「人は死をも乗り越えることができる!」
という論説に乗っかればよいのですが、この考えには嫌悪を感じてしまいます。
こんな事を考えていたら、税理士になっておけば、役人が考えるルールブックの中で数字をこねくり回しているだけでご機嫌でいられたのだろうなぁと、そんな事を思うのでした。