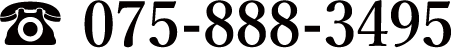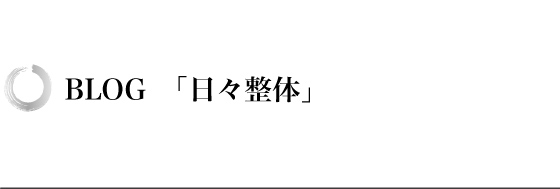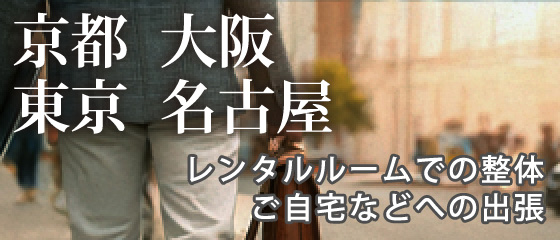良い眠りができていれば体を壊すことがありません。
ですから、体の調子が悪いということは眠りが悪いという事になります。ただ、良い眠りはなにか?ということをほとんどの人がわかっていません。
1日7時間半以上、1週間に50時間以上眠るのがよいとすることが多いようです。
しかし、実際にそれだけの睡眠時間を確保している人の自律神経の状態を確認すると、とてもよい状態とはいえません。
睡眠の状態を自律神経の働きから確認する方法は簡単です。
頭に触れてみるとすぐにわかります。理想的な睡眠ができている人の頭は適度な緊張感があります。
悪い眠りには二通りのケースがあります。
1つは、眠りが浅いケースです。ずっと夢をみている、いくら寝ても疲れが取れないなどという場合です。こんな方の頭にふれてみると、ピンと張り詰めてとても固い状態です。頭が緊張しすぎているといえばわかりやすいでしょうか。
もう1つは、眠りすぎのケースです。
眠り過ぎている人は頭の皮膚が指でつまめるぐらいゆるくなっています。眠りは長ければ長いほどいいと考えている人が多いですが、長く眠り過ぎている人は、『あたまがゆるく』なってきます。こんな状態になると、いくら寝ても眠さが取れなかったり、やる気や気力がわいてこないようになります。、もちろん頭がゆるいのですから、頭の回転も悪くなります。ちなみに、よく言われる1日7時間半以上眠っているとたいてい頭がゆるくなってきます。
自律神経の働きがよい人の頭は、適度な緊張感があります。
固くなりすぎても、ゆるくなりすぎてもいけないということです。自律神経の状態がよく、頭に適度の緊張があると1日4~6時間程度の睡眠時間で十分になります。7時間以上眠っていると、たいてい頭がゆるくなってきます。7時間も眠らなければいけないというのは、自律神経の働きがすでに悪くなっていると考える方がよいでしょう。
余談ですが、整体で体が整ってくると、
「眠れなくなった。」
と言い出す人がたまにいます。どうしてそう思うのかと聞いてみると、朝5時に目が覚めるようになったというのです。しかし、これはよい眠りができるようになったせいです。短い時間で深く眠るようになったので必要な睡眠時間が短くなったのです。
健康で元気な人は短時間の眠りですっきりと疲れがぬけます。それに対してバランスが乱れている人は、だらだらと長く眠るようになったり、寝てもトイレなどで目が覚めて何回も寝直すようになります。
体の状態は、同じ人でも季節や疲れ具合によって異なります。
それら様々な状態の人の平均をとった目安などはほとんど参考にならないと考えるべきでしょう。体の状態がかわれば、理想的な生活のリズムは変化するのがあたりまえです。7時間半眠らなければならないとか思い込んでいると、それだけで体を壊します。
「5時に起きてもすることがない。」
と言って寝なおしている人は体を自ら壊しているようなものです。
必要以上にの眠りは自律神経の働きは悪くするからです。私であれば5時に目が覚めるのなら有意義に時間が使えるようると喜ぶところです。体は活動できる状態で目が覚めたのですから、それを無視してはいけません。自律神経の状態の良い人と悪い人では生活のリズムがかわってくるのは当たり前なのです。本来は、体の状態にあわせて活動するのが自然だからです。
最後に、眠りが悪くなる原因について説明します。
「眠りが悪くなるのは、原因は交感神経の働きが悪くなることです。」
ほとんどの人は逆だと思うことでしょう。そこで、二人の人間の生活をモデルに考えてみてください。
Aさんは、趣味として山登りやスポーツをしています。体を動かして汗をかくことで、交感神経の働きが高まりますから日々元気に、健康に生活できるようになります。
一方、Bさんは、仕事や学校にいかず、ずっと家の中にとじこもってテレビをみて、3食きっちり食べて、さらに間食もして、趣味といえばパソコンのインターネットとゲームという生活です。
Aさんは精力的に、体を動かしていますから、交感神経の働きがよく元気ハツラツです。
一方の、Bさんはリラックスに満ちあふれているといえます。ストレスなど皆無といっていいでしょう。完全に副交感神経優位な状態です。
AさんとBさんでは、どちらの方がよい眠りができるでしょうか?
聞くまでもないと思ったのですが、念のために、整体にこられた方10人ぐらいに質問してみました。すると全員が、
「Aさんの方がよい眠りができると思う。」
と答えました。
どうやらたいていの方は感覚的にはわかっているようです。交感神経の働きがよい生活をしている方が深い良い眠りができるということです。交感神経の働きがよくなれば、副交感神経の働きもたかまってくるので当たり前なのですけどね。
眠りの状態を確認するときは頭のかたさを見るのが良いと説明しました。
これは、実は頭だけではありません。体の状態、生活にすべてにもいえることです。
つまり、
「緊張しすぎても駄目だし、リラックスしすぎても駄目。」
ということです。
自律神経のバランスが乱れて眠りが悪くなったとき、体がゆるみすぎである事が圧倒的に多い傾向があります。つまり交感神経の働きが悪いのが原因です。それにもかかわらず、
「眠れないのは副交感神経の働きが悪いからだ。」
ということで、まったく逆の対処をしてしまっている人がほとんどです。
息を吐いてばかりで、吸うことを考えなければ息苦しくなります。
昼間、元気に活動できる状態でなければ、よい眠りができるようにならないのは当たり前のことです。リラックスすることと、緊張することが、ともにうまくできなければうまく眠ることができなくなってくるのです。